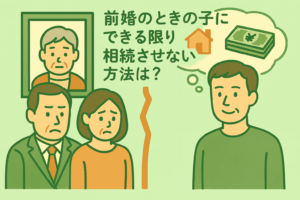
■再婚家庭での相続トラブルに注意
父または母が再婚している場合、前婚の配偶者との間に子どもがいると、相続のときにトラブルが生じやすくなります。
たとえば、父はすでに他界しており、母には再婚後の子が2人、前夫との間にも子が1人いるけれども疎遠な関係というケースを考えてみましょう。
母が亡くなると、再婚後の子だけでなく、前夫との子も法定相続人になります。
同じ両親の兄弟姉妹でも相続は揉めやすいものですが、疎遠な「片親違いの子」が加わると、遺産分割協議の難易度は一気に上がります。
では、「前婚の子にできる限り相続させない方法」はあるでしょうか?
■ポイントは「遺留分」
結論として、同じ両親の子2人だけで相続を進めることは可能ですが、前婚の子が「遺留分」を請求してきた場合には、その最低限の取り分は支払わなければなりません。
ここで知っておくべきことは、「遺留分」という仕組みです。
たとえば、このケースでは、前婚の子の遺留分は 1/6(法定相続分1/3 × 遺留分割合1/2) となります。
■前婚の子に相続をさせないための4つの方法
① 遺言書を作成する
遺言書があれば、再婚後の子にできるだけ多く相続させることができます。
ただし、遺留分(1/6)は請求されると支払う義務があります。
また、2019年7月の民法改正により、遺言執行者は相続人全員へ遺言内容を通知する義務があります。
そのため、前婚の子に知られないまま、相続手続きを進めることはできません。
また円滑な手続きのためにも、遺言執行者の指定は必須です。
たとえば遺言執行者を指定しなかった場合、銀行で預貯金を解約するときには、相続人全員の同意書の提出を要求されることが多いのです。
そのため、前婚の子が協力してくれない場合は解約できなくなります。
② 10年以上前に生前贈与しておく
母が10年以上前に再婚後の子へ贈与しておけば、原則としてその分は遺留分の対象外になります(民法1044条)。
ただし、母と再婚後の子の双方に「不当な目的(他の相続人に損害を与える意図)」があったと判断されれば、遺留分の対象に含まれてしまうため注意が必要です。
また補足として、通常の生前贈与は遺産額に持ち戻して計算されますが、贈与契約書に「特別受益の持戻し免除」を明記しておけば加算されません。
しかし、そうした持ち戻し免除がされた生前贈与についても、遺留分の対象になることは留意しておきましょう。
③ 生命保険を活用する
実務的には、この生命保険と遺言書を組み合わせる方法が有効です。
生命保険金は「受取人固有の財産」とされ、遺産分割協議や遺留分の対象にならない点が大きなメリットです。
母が再婚後の子を受取人に指定すれば、そのまま保険金を受け取れます。
また、保険金を「遺留分の支払い資金」として使うこともでき、預金を減らしておくことで遺留分の対象財産を少なくする効果もあります。
ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合は、遺留分に含められる可能性がある点に注意してください(最判平成16年10月29日)。
④ 相続人の廃除を申し立てる
前婚の子に重大な問題行為(虐待や著しい非行など)がある場合は、家庭裁判所に「相続人廃除」を申し立てて、相続人の資格を失わせることが可能です。
ただし、裁判所で認められる割合は低く(約2割)、よほどの事情が必要になります。
■ まとめ
片親違いの子とは「疎遠」で他人のような関係であることも多く、いざ相続が発生したときの話し合いは難航しがちです。
そのため、結局は、遺留分の請求を受けることを想定して対策を立てる必要があります。
当事務所では、相続に強い税理士やFP(ファイナンシャル・プランナー)と連携し、遺言書・生前贈与・生命保険などを組み合わせた遺留分対策のご相談にも対応しております。
「誰に財産を遺したいのか」を明確にし、再婚後の子が無用な相続争いに巻き込まれないように準備しておきましょう。
▶️まずはお気軽にご相談ください。
無料相談のご予約はこちらからどうぞ。
https://souzoku-omamori.com/contact/?id=contact