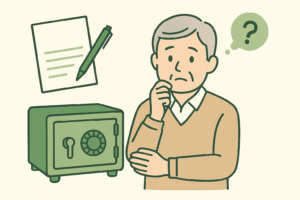
「遺言書を書いたけど、どこにしまっておけばいいのか不安…」
そんなご相談をよくいただきます。
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば誰でも作ることができます。
でも“どこに保管するか”によって、遺言が有効な内容か、発見してもらえるか、大きく左右されてしまうのです。
実際にあったトラブル例や、主な保管方法の特徴をもとに、注意すべきポイントを解説します。
■ 保管場所① 銀行の「貸金庫」
「安全そうだから貸金庫にしまっておけば安心」と考える方は少なくありません。
たしかに、破棄や改ざんのリスクは抑えられますが――最大の落とし穴があります。
それは、亡くなった後に貸金庫が開けられない可能性があるという点です。
銀行では、貸金庫の開扉にあたって「相続人全員の同意書」を求めるのが一般的。
もし遺言書が特定の相続人に有利な内容であれば、他の相続人の協力が得られず、遺言書を取り出すことができない可能性があります。
また、遺言執行者を指定していても、肝心の遺言書が貸金庫内にあるかぎり、その内容どおり執行することができません。
さらに、開扉するには戸籍謄本などの相続関係書類の準備や、銀行とのやりとりが必要です。
そのため、中身を確認するまでに数か月かかることもあるため、それまで相続手続きができないことに注意してください。
■ 保管場所② 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」
2020年7月からスタートした、法務局による保管制度。
大きなメリットは、遺言書を安全に保管でき、亡くなった後の家庭裁判所の「検認」も不要にできる点です。
【主な特徴】
・事前に予約し、遺言者が法務局(住所地・本籍地・不動産所在地のいずれか)に申請
・法務局が「保管証」を交付
・死後に相続人が申請すれば、遺言書の「内容証明書」を取得できる
・他の相続人や受遺者の住所にも、「遺言書が保管されている旨の通知」が郵送
【注意点】
・制度独自の作成ルールがあるため、書き方を間違えると保管してくれない
・A4用紙、所定の余白、財産を渡す相手の住所記載などが必要
・遺言書のコピーは渡してくれないため、事前に写真やコピーを取っておくこと
■ 保管場所③ 自宅の金庫、机やタンスの引き出し
最も多いのが、自宅内に保管するケースです。
ただし、相続人による改ざんや破棄のリスクがあるため、信頼できる家族以外には、保管場所を伝えない方も多いです。
その結果、「誰にも気づかれないまま、遺言書が見つからなかった」――という事態も起こります。
■ 保管場所④ 信頼できる専門家に預ける
司法書士や弁護士など、第三者の専門家に預ける方法もあります。
この方法なら、遺言書の保管だけでなく、書き方のチェックや法的なアドバイスも受けられるため、内容の不備による無効リスクも防げます。
■ 遺言書の存在は、家族に「知らせておく」ことも大切
どこに保管するにせよ、大切なのは「そこに遺言書があることを、誰かが知っている」ことです。
誰も知らなければ、せっかくの遺言も発見されず、大事な家族に遺した想いが、全部無駄になってしまうからです。
■ まとめ
遺言書は、書いたら終わりではありません。
「故人の想いをきちんと実行すること」こそが、本当の目的です。
でも保管方法によっては、その大切な想いが届かなくなることもあります。
そのため、信頼できる専門家と相談しながら、「守る・見つける・実行する」保管場所を選びましょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成だけでなく、自筆証書遺言の作成から保管まで、安心してご相談いただける体制を整えております。
「遺言書を書きたい」
「でも、保管が不安・・」
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。
▶️無料相談のご予約はこちらからどうぞ。
https://souzoku-omamori.com/contact/?id=contact